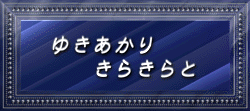
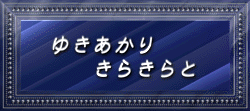
By miyukiさん
「・・・ちゃん、・・・にーちゃんっ」
ふと、誰かに呼ばれたような気がして、少年は意識を眠りの底から浮上させる。
そして、もぞもぞと身体を動かし、隣にあるべきぬくもりを引き寄せようとして・・・そこにそのぬくもりがないことに気付いた。
「・・・・・・?」
違和感を感じて少年は目を開く。
・・・と、視界いっぱいに飛び込んでくる少女の笑顔。
「おにーちゃん、おはよっ」
「どっ・どーした?まだ、夜中だろう?な・なんで、起きて・・・?」
身体が報せる現在時刻は、真夜中を少し過ぎたといったところである。
いつもならば、父の言い付けを守り、夜は早くに寝て、そのまま朝までぐっすりの妹が眠気など少しも感じさせない表情で自分を覗き込んでいる。
普段では考えられない光景に、さすがの少年も顔いっぱいに疑問を浮かべて起き上がらざるをえなかった。
だが少女は、そんなことを全く気にせず嬉しそうに兄の腕にしがみつき、顔を見上げてきた。
「あのね、まどのそと、あかるいの!おつきさまのじかんなのに、あかるいのっ!」
「え・・・?」
妹に言われて初めて気付く。
たしかにカーテンの隙間から、明るい光が差し込んできている。
(今日は、満月じゃないのに・・・?)
訝しげに光源について思案する兄の腕を、少女はくいくいとひっぱり、にっこりと笑った。
「それでね、ゆきがね、いっぱいなの。すごくきらきらしてるんだよっ」
「・・・っ!そうか、雪明かりか・・・!」
納得のいった少年は、そのまま妹を腕に抱き上げて、勢いよくカーテンを開く。
「・・・・・・っ!!すご・・・い、積もって・・・」
「こぉんないっぱいのゆき、はじめてだよねっ♪」
興奮したように兄のパジャマを握り締めた少女の視線は、窓の外に釘づけである。
少年にとってみても初めての風景は、少年から声を奪い、感情を高まらせていく。
「・・・ね、おにーちゃんっ」
「うん、そうしようっ・・・!」
顔を見合わせ、笑顔で頷きあった二人は、上から雪が落ちてこないようにそっと窓を開け放つ。
途端に暖かい部屋の中に入り込んでくる冷たい風。
それを受けて、二人は体を震わせた。
「さむぅぅいっ」
「やっぱり冷えてるなぁ・・・ちょっと待って」
一度窓を閉めて、妹の身体をベッドにおろし、てきぱきと防寒具を取り出す少年。
「とりあえず、マフラーと耳あてと、コートと・・・もう一枚ズボンをはいて・・・セーターも着ておいたほうがいいかな・・・手袋は、するか?」
「ゆきにね、さわりたぁい」
「じゃ、コートのポケットに入れておくから、冷たくなったらすぐにするんだぞ」
「うんっ!」
慣れた手つきで妹にそれらを着せてから、少年も身仕度を整える。
「準備、完了」
「いこうっ、おにーちゃんっ!」
「よしっ!」
そしてもう一度窓を開け放ち、妹を抱き上げたまま少年は呪文を唱える。
「・・・『浮遊』!」
ふわり・・・、窓から飛び出た二人はそのままゆっくり空中散歩としゃれこんだ。
「よく積もったなぁ・・・そこら一面、真っ白だ・・・」
「すごいねぇ・・・これぜんぶゆきでしょう?」
「そう。これだけあったら、好きなことして遊べるよ」
「たのしそう〜。・・・でも、もうふえないんでしょう?」
「そうだなぁ、もう止んじゃってるから・・・これ以上は積もらないだろうなぁ・・・また、雪が降り始めたら増えるだろうけどね」
「ざんねん〜。でも、でも、あたしたち、このゆきにいちばんのりだよねっ?」
「そ。オレ達が一番乗りだよ。だって、誰の足跡もないだろう?」
「うふふふふ〜」
兄の言葉に、少女は嬉しそうな表情を隠しきれずに兄の首にしがみついた。
「ん?どした?」
「あのね、あのね、どさっ、てね、おちてみたいのぉぉっ!」
「・・・雪の上に?」
「うんっ!まえにね、おとーさんが、おかーさんといっしょに、いっぱいのゆきのうえでそうやってあそんだんだってっ!いちばんのりの、『とっけん』なんだっっ!いっぱいゆきがふったときにやってごらん、っておとーさんがゆってたのっ!」
(・・・母さんが、父さんを雪の上に吹っ飛ばしたんじゃなくて・・・?・・・いや、こんなシチュエーションだったら、父さんなら抜け目なく母さんも抱き込んで一緒に落ちて遊んでるか・・・)
なんとも親の行動パターンを熟知している息子であったが、今はとりあえず目の前のお姫さまの要望を叶えるか否かについて頭を使うことに決めたらしい。
(危なくない方法って言うと・・・・・・って、そっか、その手でいいじゃないか)
「・・・おにーちゃん?だめ?」
残念そうに顔を覗き込んでくる妹に、少年はにっこりとお日さま笑顔を返す。
「ん?じゃあね、一回実験してみよう。で、恐くなかったら、もう一回やるっていうことで」
「じっけん?」
小首を傾げる妹の身体をぎゅっと抱き締めて、少年は1メートルくらいの高さで呪文を解除した・・・。
「うにゃぁぁぁっっ」ポスン・・・ッ!
重力による自由落下で雪の上に落ちる二人。
少女をかばうように少年が背中から落ちたが、新雪の上ということもあり、特に痛みは感じていないようだ。
無論少女は無傷のうえ、今の体験で頬を紅潮させて興奮していた。
「恐くなかった?」
妹の様子にクスクス笑いながら問いかけた少年の上で、少女はバタバタと腕を振り回す。
「もういっかい〜!おにーちゃん、もういっかいやるぅぅ!!」
「今のでいい?それとも、一人の方がいい?」
「おにーちゃんといっしょがいいっ!」
「よしっ!」
一度立ち上がってとりあえず雪を払い落としてから、もう一度少年は『浮遊』を
かけ、先程と同じくらいの高さまで飛び上がる。
「いくぞっ!」
「うんっ!」
兄の言葉に、少女はぎゅうっ、と兄の胸元にしがみつき、瞳を輝かせる。
そんな様子を見て取って、少年は呪文を解除した。
「うきゃぁぁぁっっ」ポスン・・・ッ!
またしても、無事着地。
「・・・どうだった?」
「もういっかい、もういっかい〜!!おにーちゃぁぁんっ!!」
胸元に、ぐりぐり頭を擦り付けて、少女は兄にねだり倒す。
どうやら殊の外、この遊びが気に入ったようだ。
少年はそんな妹の様子にクスクスと笑い、胸の上の少女を抱き上げた。
「何度でも、飽きるまでお付き合いしましょう、お姫さま♪」
ふと目が覚めたリナは、隣にガウリイがいないことに気付く。
「・・・あれ?」
「お。起きたのか、リナ」
「ガウリイ?」
窓側から聞こえた夫の声に、リナは身体全体で振り返る。
するとそこには柔らかな笑みを浮かべたガウリイが、窓から差し込む光に照らされて立っていた。
その姿にしばし見惚れたリナだったが、光源を悟り、布団の中で苦笑いを浮かべた。
「これ、雪明かりね?・・・ってことは、随分と積もってるって事?」
「ああ。久しぶりの大雪だぞ。庭の柵、半分くらい埋もれちまってる」
「はぁ〜、雪かき大変そうね〜・・・。まぁ、ウチには肉体労働専門員がいるから、あたしには関係ないけど・・・」
「おい、『火炎球』でもいくつか打っ放せば、それでカタつくだろうが・・・」
あっさり言い放ったリナの言葉に、ガウリイが憮然とした表情を返す。
「あら、溶かしちゃったら子ども達が遊べなくなっちゃうでしょうが。だ・か・ら、雪かきするのよ、お父さんっ♪」
髪をかきあげながら、殊更にっこりと笑うリナに、ガウリイはクスクス笑いながら窓の外を指差した。
「もう充分、遊んでるけどな」
「え?」
ガウリイの指に導かれるようにリナはベッドから起き上がり、ガウリイと並んで窓の外を見る。
と、そこには・・・
「・・・ちょっとぉ・・・今、何時だと思ってるわけ・・・あの子達は・・・」
がっくりと肩を落として頭を抱えるリナ。
窓の外では雪まみれになりながら、はしゃぎまわっている子ども達の姿があった。
「もう三十分にもなるんだが・・・まだ飽きてないみたいだぞ」
「三十分!?んもーっ、なんで止めないのよっ!風邪でもひいたらどーするのっ!?」
「念入りに防寒してるから大丈夫だろ?そこんとこは抜け目ないぞ、あいつら」
「いや、そーゆー問題と違うから・・・」
「それに、風邪ひく前には戻ってくるって。そこまで羽目を外しすぎはしないだろう」
「・・・まぁ、こんなたくさんの雪を見ちゃったら、我慢できないだろうけどさ・・・・・・しかた、ないかぁ・・・全く」
窓の外で楽しそうに遊ぶ二人の子どもを見て、リナは諦めたように小さく呟きながら苦笑した。
「そうそう、朝になったら多少なりと溶けちまうんだし、今のうちに遊びたいだけ遊ばせてやってもいいんじゃないか?」
「・・・だからって、母親としてはこのまま黙って寝なおすわけにもいかないけどね」
「リナ?まさかお前まで外で一緒に遊ぶのか?」
驚いたようにリナを見つめてくるガウリイに、リナは憮然とした表情を返す。
「あんたねぇ・・・あたしまで遊んでどうするのよ!そうじゃなくて、準備しなくちゃ、って言いたいの、あたしは!」
「準備・・・?」
ガウリイの疑問を含んだ眼差しを受けて、リナは母親の顔で小さく微笑んだ。
「お風呂の準備。遊びおわったら、冷えた身体を暖めないとダメでしょう」
「なるほど・・・」
「ついでに軽い夜食でも作っておきますか。どうせ、お腹すかせてるだろうし・・・・・・今日は、特別に・・・っていうことで」
「手伝いましょう、奥さん。・・・ついでに、オレの分も作ってくれると嬉しいな」
身体を引き寄せられ、触れるだけの口づけを受けとめながら、リナはクスクスと笑った。
「じゃ、特製パンケーキでも作りますか」
「お。ラッキー」
雪明かりのみに照らされながら、二人は今一度口づけを交わし・・・体を寄せ合いつつ寝室を出ていくのだった。
「うにゃぁぁん、いっぱいあそんだぁ〜♪」
少女は雪の上にちょこん、と座って満足気に笑う。
「・・・ちょっと、寒くなってきたかな・・・?そろそろ戻ろうか?」
「うんっ!あしたもまた、あそべるよね?」
「母さんが父さんとじゃれあって、炎系の魔法でも打っ飛ばさないかぎりは大丈夫だと思うよ」
ひょい、と妹を抱き上げて、少年はいたずらっぽく笑う。
「じゃあ、おとーさんに、おかーさんのことからかっちゃだめよ、ってゆわなくちゃ」
おませにクスクスと笑う少女に、先ほど作った雪兎を手渡しながら、少年は優しく呟く。
「そうだな・・・でもきっと、父さんも母さんも、一緒に遊んでくれると思うけどね」
「そーだねぇ。だけど、おとーさんたちがいっしょでも、おにーちゃんも、いっしょにあそんでね?」
「もちろん。明日は、こんな小さな雪兎じゃなくて、大〜きな雪だるまを作ってあげるよ」
「ほんとに!?ほんとのほんとに!?」
「ん。約束」
「やーくそくっ!」
額を寄せて笑いあった二人は、家の方向に向き直る。
・・・と。
「あ・・・れ?明かりが、ついてる・・・?」
「ほんとだぁ・・・おかーさんたち、おきてるのかなぁ・・・?」
さくさくと雪を踏みしめて家に近付くと、ふいに玄関のドアが開き、両親が顔をのぞかせた。
「もう充分遊んだんでしょう?早く戻ってらっしゃい」
「風呂とおやつの用意できてるぞ」
「父さん、母さん」
「おやつなぁにぃ〜?」
兄の腕の中からそう叫ぶ愛娘に、ガウリイとリナは苦笑するが、ゆっくりめの歩調を急かすべく、同じく大きな声を返した。
「お母さん特製パンケーキよっ!あったかいのが食べたかったら、早く戻ってらっしゃいっ!!」
『やったぁっ♪』
途端に駆け寄る子どもたちを迎え入れて、玄関の扉は静かに閉められる。
そして子どもたちはこの夜、湯上がりのホクホクの身体で、初めての『真夜中のおやつタイム』を経験したのだった・・・。
翌日。
夜のはしゃぎぶりがたたって、昼近くまで目が覚めなかった子どもたち。
あいにくの晴天により、起きだした頃にはだいぶ雪が溶けてしまっていて、思うように遊べなかった妹姫のご機嫌は随分と低空飛行だったらしい。
だが、リナ並の高さの大きな雪だるまを兄にプレゼントしてもらい、一気にご機嫌が回復したとのことである。
そしてこの少ない残り雪で、一体どうやってこんな大きな雪だるまが作れたのか不思議がる両親に・・・「お兄ちゃんは妹との約束を守らないとね」
と、言って笑う少年の姿があったとか、なかったとか・・・。
なんにせよ、今日もガブリエフ家は幸せオーラ満載のようである。
★End★