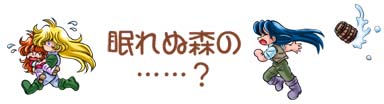
<<前編>>
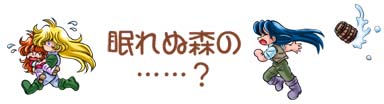
<<前編>>
昔々、ある所に、とても美しいとある国がありました。
その国では、人々は勿論のこと、精霊族や竜族たちでさえも、皆が仲良く、幸せに暮らしていました。
それは、王の政治の評判がとても良いものだったことも事実ですが、もっとものその理由といえば、多種族の交流による異文化コミュニケーションが盛んだったことにあるでしょう。
お互いの足りないところを補い合い、助け合う、理想の国。
平和な毎日の中で、人々の心は常に穏やかで優しく、争うことをまるで知らないかのようでした。
街を歩けば、人々の笑顔と笑い声が満ち溢れていました。
――そんな中を。
ごく一般の、一人の市民が、しかし、皆の視線を全て集めながら――今日は珍しいですね。難しい顔で歩いていました。
「おや、国王様、こんにち……?」
一人のおばさんが、いつものように明るく、その一般市民の格好をした国王様に声をかけました。
この国では、王様がこんな格好をして歩いているのは、日常茶飯事なのです。
ですから皆は、驚きはしませんでした。
しませんでした――が。
声をかけたおばさんは、はたと挨拶を途中で止め、首を傾げました。
いつもなら立ち止まって、『こんにちは、今日は良いお天気だね』とでも言いながら、笑顔を向けてくるはずの国王が、立ち止まることなく、まるでこちらに気づかなかったかのように――いえ、実際気づかなかったのかもしれませんが――通り過ぎてしまったからです。
他の場所でも、そんなことが起こっているようでした。
王様が通った後には、国民の、何かを不思議に思うような、不思議な雰囲気が残されてゆきました。
国民の笑顔を愛し、それを見るために一所懸命働く王様。
無論この両者は、お互いを信頼し合い、愛しあっていましたから、国民の動揺もかなりのもののようです。
――つまりは。
どんなに理想的な国があろうとも、問題、というものは必ず起こる、というわけでして――。
この国にも、たった一つだけ、普段はのんきで優しい国王を、こんなにも困らせてしまうような、大変な問題がありました。
それは、というと――……
「一体、王子はいつ帰ってくるのやら――」
そう。
王子が城を出てから、もう数ヶ月。
大事な跡取り息子が帰ってくる気配は、一向にありませんでした。
今日も国王は、執務室で一人、ため息をついています。
――あいつは確かに強いが、上には上がいるかもしれん。それに、私もそろそろ、引退しようと思っているのだが――。
まだ誰にも伝えたことの無い意思を心の中で呟きながら。
旅に出てしまった冒険家の王子を、父親らしく、又、一国の長らしい意味でも心配に思っている男が、そこにある大きな椅子に、ぽつんと腰掛けていました。
妙にその背中が、今だけは頼りなさげに見えました。
「なぁリナー。本当にこの先に用事なんてあるのかぁ?」
「あるっていってるでしょうが!!そもそもっ!なかったらこんな所まで連れてこないわよ!疲れるし!暑いし眠いし!お腹すくし!ひもじいし!!」
「いや、ひもじいってゆーのは、この際どうでも良いような気が……」
「うっさいよ!ガウリイ!!あんたは黙ってついて来れば良いの!!」
「ふぁーい……」
――そんなこんなで。
鬱葱とした森の中を、一組の男女が、ドつき漫才なんぞをやりながら歩いていました。
ハッキリ言って、この森の雰囲気には全然似合わないのですが――それをあえてつっこむことはしないでおきたいと思います。
二人のラブラブ漫才は、端で見ているのが一番楽しいのですから。
「良い?あたしはあんたを一目見て、『あー、この人だわv』って思ったの!だからあんたも、きちんとあたしの言うこと聞きなさい!」
「いや、お話の筋が通ってないんですけれど……」
「そんなことより!さくさく歩くっ!!」
「人のこと逆ナンパしておいてこれかよ……ったく、人使いの荒いお嬢ちゃんだなー」
「んですって!!もう一度言ってみなさいよ!!」
「あああ、いえいえ、なんでもありま……せん」
隣を歩く小柄な少女、リナ――栗色の髪を長く伸ばし、紅い瞳を持った、愛らしい感じの村娘に、どんな恐怖を覚えたのでしょうか。
金の長髪を長く風と戯れさせながら、蒼い瞳で、いつどんな敵が出てくるかもわからぬと、周囲に気配りを忘れていない剣士スタイルの男、ガウリイは、言葉の後ろを小さくひっこめつつ、少女の怒鳴り声に答えたのでした。
――実は、この少女と青年が出会ったのは、ほんの1、2ヶ月前ほど。
少女の方が、ここからいくつか前の街で、青年に声をかけたのが、今一緒に居る最もな理由でした。
ですがなぜなのでしょうね。
この二人の息といったら、それはもう、大分昔からお互いを知っているかのように、素晴らしく合うものでした。
このような漫才も去ることながら、実は戦闘でも、二人のコンビネーションは最高のものなのです――剣の腕だけは、人間離れしている青年と。魔法の腕前が、尋常ではない少女と。
作戦会議も無しに、二人はいくつもの敵を、難なくすぺぺのぺのスペシャルスピードで倒してきたのです。
不思議な二人組みです。
実は、この森の中に入ったばかりの時も、二人は、かなりの数の敵を、ことごとく打ち破って来たのです。
青年が周囲に気配りを忘れないのも、そのせいなのですが――先ほどから、魔物が全く出現しなくなってしまったのは、一体なぜなのでしょうか。
気配を感じることはあっても、殺気を感じることはありませんでした。むしろ、怖がるようなオーラが、可哀想なほど、全身からにじみ出ていて……。
――ともあれ。
こうして夫婦漫才を続けながら、二人は暗く、昼間だというのに光のろくに差し込まないような森の中を、進んで行ったのでした。
――壁。
あれからしばらく進んだ先には、そうとしか言い表せないようなものが、二人の目の前に立ちふさがっていました。
太いツルが、頑丈にお互い、絡み合っています。それが、天高く、どこまでも伸びているのです。
……リナがそこで、ふぅ、とため息を付きました。
「……着いたわ」
「つ、着いた?」
感慨深気に呟いたリナは、その自らの腕で、おでこの汗をぬぐっていました。
ガウリイが、思わず、驚きに声をあげます――着いた?これが何だって言うんだ。
が、疑問を口に出すことはありませんでした。
リナのことだから、何か考えているのだろう。そう思ったのです。
考えるのが面倒くさかった、ということは、絶対誰にも秘密なのです。
――ガウリイは、肉体労働は大得意でも、頭脳労働をスライム並に苦手としていたのです。
おかげで、くらげくらげとリナにドつきたおされる毎日なのですが……。
「ねぇ、ガウリイ。不思議に思わない?」
「何が?」
天を見上げ、太陽の光を顔に浴びながら、リナが呟きました。
「ここだけ木が無いの。ここは森の中よ――ね、不思議でしょう?」
「ああ、そういえば――」
太陽の光をさえぎる木の葉も無く、ここだけ直接、温かいような気がする。
太いツルでできた緑の壁が、太陽にキラキラと美しいものでした。
……リナが、さらに続けます。
「と、いうわけで。伝承では王子様だったんだけど――まぁ良いや――ってことで、あんたがこれからここに入るのよ」
「……おうっ!」
と、いつものように返事をしかけて――
「って、どえぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇっ!!」
こちらを見ているリナの方に、緑の壁から視線を戻し――瞬間。ガウリイは、心のそこから叫び声をあげていました。
突然、真っ青になった顔をしながら、リナの方を指差し、かぽんっ、と口を開けたまま、動かなくなりました。
リナはその様子に、
「何よガウリイ。うるさいわね……!」
ガウリイとは反対に、きわめて冷静な様子で、真っ白なマントを太陽の光になびかせながら、言いました。
そのまま、「準備は良いの?」と隣のガウリイに問い、どこから出してきたのでしょう。魔法使いの使う、典型的な形の杖をその緑の壁の方に向けながら、
「ひら……」
「ちょっとまったぁぁぁぁぁぁぁぁっ!!」
呪文のようなものを唱え始めた少女を、ぐわしぃっ!と、青年は、心穏やかではないような様子で、突然羽交い絞めにしました。
「ち、ちょっとぐぅあうりぃ……!!く、ぐるしひ……!」
「お前、いつのまに着替えたんだ?!俺だって男なんだぞ!そんなことして良いと思ってるのか?!しかも、白なんて……似合わな……!!」
「黙れ貴様はぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ!!」
ばぐべし!!
なんだかあまり、聞きたくないような音がたったと思った瞬間、今度は青年の方が、地面にキスをしていました。
リナは、たった今けり倒した青年の背に、思いっきり杖を付き立てると、
「んぐえっ!!」
「あたしがあんたの前で着替えるかっ!しかも!白が似合わないとは何よ!じゃあ、何色だったら良いってーのよ?!」
「勿論黒に、決まっ……」
げすげすっ!
「ぐえぐえっ!!」
――そうしてガウリイ君は沈黙しました。
「ふん」
他愛ないと、杖を地面にぐっさりと付き立てると、リナは一つ、ため息を付きました。
……確かに改めてみると、リナは、いつのまに着替えたのでしょう。
先ほどまでの村娘風スタイルはどこへやら、今はいわゆる魔女――の格好をして立っていました。
帽子から足元まで、全身白なのですが、確かにガウリイの言うとおり、彼女のような性格の女には、黒の方が似合っているのかもしれません。
こんなことは、決して言ってはならないのですが。
そうして少女は、改めてため息を付いて……後ろでなにやら、杖でさされた所から、でしょうか……とにかく、煙を立てているガウリイを無視して、緑色の、天高くある壁へと向き直りました。
そうして、杖の先を、壁に向けて、呪文を唱えました。
無論、その呪文とは――
「ひらけ〜!ゴマ!!」
……かろうじて意識を保っていたガウリイのそれは、そこで完全にブラック・アウトしたのでした。
――こんな軽薄な世界があってよいのだろうか。
と、ガウリイは、久しぶりに哲学的なことを考えていました。
おかげで、知恵熱が出てきそうなのですが――。
しくしくとする背中の痛みを我慢しながら、リナから聞いたお話はこうでした。
『ねぇ、ガウリイ、眠り姫、ってゆー童話、知ってる?あー、そう、知らないのね。つまりはこのお話、単純に説明すると、悪い魔女に眠らされたお姫様を救いに、王子様がやって来る、ってゆーお話ね。聞いたことがあっても、覚えてないのかもしんないけれど。というわけで。実際そんな童話のようなお話が、こんな所にも存在する、ってゆーこと。実はね、あたしのばーちゃんが、その良い魔女――あぁ、王子を姫の元にエスコートする役のことね――だったんだけど、心臓発作でぽっくり逝っちゃって。かーちゃんには魔法の才能が全く無いし、ねーちゃんは忙しいらしいから、その役があたしに回ってきていた、ってゆーこと。さっきも言ったとおり、この伝承ではやってくるのは王子様なんだけど――まぁ、あたしの直感に間違えはないだろうし?というわけで、あんたがこれからお姫様を救いに行くのよ。噂によれば、ここの姫も相当綺麗だったそうだけど』
……というものでした……。
ガウリイは寝ないように努力しつつも、適当にこのお話を聞き流し――
そうして。
この世界のありかたについて考えたのでした。
……勿論過去形です。
10秒足らずで止めてしまったのですから。
ガウリイはリナに気づかれぬように、そっとため息を付きました。
――緑の壁を、リナのこれまた軽薄なことこの上ない呪文で突破した後、大きなドアも、適当に開けて入り。
どうにもこうにも見慣れない、白い魔女姿のリナと共に、美しい城の中を歩き回り――と。
ふと、不意に、疑問が起こりました。
何事も無いかのような顔で、歩みを進める白い魔女に、
「そーいえばリナ。なんだか城の中、人が住んでるかのように綺麗だぞ?」
「あぁ、使用人さんたちも実は居るのよ?眠らせてあるの。――お城ごとね。お姫様がおきた時、誰も居なかったら寂しいでしょう?だから、丸ごと封印したってことよ」
「ふーん……」
と、適当に相槌を打っているうちに、なんとお姫さまの寝室に、もうはや着いてしまったのでした。
そのことをリナに教えられたガウリイは、驚いてしまったようでした。
――お姫様の寝室。
まさかこんなにあっという間に着くとは思っていなかったのです。
……リナがそっと、ドアへと向き直りました。
そうして、一言。
「封除(アンロック)」
ドアノブの辺りに、手を当てて、小さく呟きました。
すると……。
カチャリ。
どうやら鍵が、呆気なく開いたようでした。
そうしてリナが、ガウリイの方を、そっと見上げました。
そこから何を感じ取ったのでしょうか――ガウリイが、リナの視線にモノをいわれたように頷き……ドアノブを、彼女に代わってとりました。
キィィ……。
ドアは、小さな音を立てて開きました。
まず最初に、お部屋の中を一望したリナが、一言漏らしました。
「うあ、めちゃめちゃ豪華……」
……そう、そこには。
美麗、という言葉では足りぬほどに、美しいお部屋があったのです。
どっからどう見ても、高級品としか見えないようなものの数々。
クリスタルのテーブルを、センス良く中央に、全体的にお姫様らしく、乙女チックに、ピンク系統の色で統一したお部屋。
――リナの商人魂がうずき始めたのは、言うまでもありません。
「うっし、一仕事終わったら、とりあえずはあれとあれを――礼金代わりにもらうとするか。ただで助けてもらえると思ったら大間違いよ!んふ、んふふふふふふ……」
「…………」
ガウリイは知らないのですが――実は、リナの実家は商売をやっているのです。
魔女の家系が商売……世の中、変わったことも多々あるようです。
――ともあれ。
ガウリイは、リナの後に部屋の中を覗いた瞬間、とある一点を、真っ先に指差しました。
「……あれは……」
「うみゅ、棺桶だわ」
「棺桶……?」
「ほら、死んだ人を詰め込む箱のようなもののことよ」
「いや、それは知ってるんだが……」
桃色のベッドの上には、確かに一つ、丈夫そうな鎖にぐるぐる巻きにされた棺桶が置かれていました。
……棺桶。
リナの話によれば、お姫様は生きていたのではなかったのか。
「なぁリナ、棺桶の中に、生きてる人を詰め込んでも良いのか?」
「はぁ?良いわけ無いじゃない。まぁ、悪人なら詰め込んで、そのまま埋めちゃっても良いけどねv」
さり気に怖いことを言います。
やっぱり、白い魔女服なんぞ、全然似合ったものではありません。
これが黒だったら、どんなにサマになるものなのか……想像すると、少し恐ろしいかもしれません。
ガウリイは背筋に、何か冷たいものを感じたようでした。
……と。
気がつけば、リナがなにやら、懐の辺りをごそごそと探っています。
「……何か探しているのか?リナ……」
しかし、リナは黙ったまま、それを続けています。
一向に、返事をしてくれる気配すらありません。
熱中しすぎて、ガウリイの声に気づいていないのでしょうか――相手にしてもらえなくなったガウリイは、仕方なく、部屋を隅々まで見渡しました。
……可愛らしいぬいぐるみの数々に、美しい家具。テーブル、椅子。ソファー。シャンデリア。壁の装飾も美しいし、カーペットの模様も文句のつけようがないものでした。ちなみに、それらが全て調和していて、一つの安らげる空間を作り出しているように感じられました。
自然と、ため息が漏れます。
「あったっ!!」
と、不意に、リナが声を上げました。
ガウリイが振り向くと、突然彼は、リナに腕をとられます。
「っ、いてて、何するんだ?突然」
「良いから!手、出して!」
「ん、こうか?」
「そうよ……はい、これ。これであたしの仕事はお終い」
「……?」
手に、冷たい感触。
言われて、ガウリイの手の上には、リナの小さな手から、何か金属のようなものが置かれました。
リナが、握っていた手をそっと開き、ガウリイの手の上から取り去ります。
すると……
「鍵、か?」
「ええ、棺桶の鍵よ。さぁ、早く開けて、ちゃっちゃとお姫様を起こしてやって頂戴」
「……俺が、か?」
「他に誰が居るって言うのよ?」
「どうやって?」
「そ、それはぁ……」
……ガウリイの手の上に乗っかっている、小さな鍵を見つめながら、リナは複雑な表情を浮かべているようでした。
先ほどまでの笑顔や怒った顔はどこへやら。
今は、どこか悲しそうな顔をして、無理やり微笑んでいる、といったような表情をしています。
「……リナ?」
「……さ、さぁ!とにかく、それはアレを開けてから考えましょう!!ね!」
その理由がわからずに、不思議を抱えたガウリイの背が、リナによってどんと、力強く押されました。
「おい?」
少したたらを踏んだ先で、ガウリイはそっと、振り返りました。
ですがしかし、
「早く行きなさい!この馬鹿くらげ!!」
言われて、仕方なく棺桶の方へと向かうのでした。
……この時の、リナの気持ちを知る術は、ガウリイにはありませんでした。
<<つづく>>