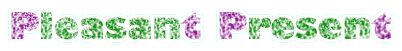
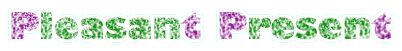
どんどんどん……
突然降り出した激しい雨の音に混じって、ドアを叩く音がしていた。
「誰じゃ…、こんな天気に…」
不快さを隠そうともせず、いつにも増して険しい顔の老人はゆっくりとした足取りで、その音を止めるために玄関へ向かった。
「おう! じーさん。ひでえ天気になったなぁ」
天気の鬱陶しさとは正反対の調子で、金髪の青年がドアの向こうから顔を出した。
「…おまえさんか。
何の用だ?」
彼は意外そうな表情を浮かべると、大事そうに抱えていた包みを、老人の前に差し出した。
「いつもの配達だって。
天気が悪くたって、メシは食うだろ?」
再びにこにこと笑みを浮かべた青年の大きな身体からは、ぽたぽたと滴が落ちている。
小柄な老人は、小さくため息をつくように呟いた。
「いつまでもそこに立っていると、その辺が濡れる。
さっさと入って乾かさんか――ガウリイ」
「勝手に薪をくべろ。
わしは動くのがしんどいんじゃからな」
「ああ、わかってるって」
ガウリイは、老人の棘のある言い方を、いっこうに気にしている様子もない。
まるで我が家のように、勝手に自分でタオルを調達し、火を熾している。
白髪の老人の方は、側の椅子に腰を降ろしたまま、彼の動きを追っていた。
「―――こんな天気に配達に来るとはな。
また雑貨屋の末娘が言い付けたのか」
「ん?
何だかわかんないけど、今日はオレ、家にいない方がいいとか言われてな。
こんな天気じゃ、外で昼寝ってわけにもいかないから、それじゃ、じーちゃんトコに配達に行くかなって思ってさ」
「暇つぶしか」
タオルで長い金髪をくるんだガウリイは、軽く笑う。
「まあ、気にすんなって。
別に誰も困んないから、いいだろ?」
老人は、またため息をつく。
こんな会話をするようになってから、どれくらい経つだろう。
この男が初めてこの家に来た時は、まともに話した覚えもないのに。
雑貨屋の末娘が、婿を連れて旅から戻って来た、という話を耳にしたのは、その後だったはずだ。
傭兵をしていた剣士だとも聞いたし、実際ここに来る時も、常に剣を腰に差している。
けれど、そんな剣呑な雰囲気は全く感じさせないどころか、いつもやたらと明るく、幸せそうだった。
まあ、相手があの雑貨屋の末娘でも、新婚は新婚だ。
他人には理解出来なくても、彼なりに幸せなのだろう。
老人は街から遠い、長い坂の上に居を構えている。
すでに身内もおらず、寄る年波で足がおぼつかなくなったので、何年か前から、その雑貨屋に生活の品々の配達を頼んでいた。
こんな田舎では傭兵の仕事などそうそうあるはずもないのか、女房の実家の手伝いと称して、それは青年の仕事となったようだ。
それも、主の時は一日おきだったものが、この男になってからは、本業のある日以外は毎日になっていた。
ある時、「物好きだ」と皮肉った老人に、彼は笑って。
「鍛練になるからな。じーちゃんも退屈しのぎになっていいだろ?」
万事がこの調子だった。
独りで暮らすようになって幾年、今では自分でも認める程、偏屈で無愛想になったこの年寄りに、彼はごく自然に接してくる。
気負うことも、媚びることも、怒ることもなく。
時折、八つ当たり的な言動をして、居心地の悪い思いをさせてしまったはずの翌日でも、まるで何もなかったかのように、いつも通りの姿でやって来る。
雑貨屋の主一家や街の連中は、「あれは天然だから」などと呆れたような評価をしていたが、老人にはそれだけでないような気がしていた。
おそらく、彼がそれを他に見せることはないだろうが。
―――自分のように。
「飲むか?」
唐突に、目の前に湯気の立つカップが差し出された。
顔を上げると、いつものようににこにこと笑ったガウリイが、もう一方の手に自分の分を持って立っている。
「自分の家のようじゃな」
これまたいつも通りの皮肉まじりの答え。
「これだけ毎日来てりゃあ、な」
ガウリイは軽くウインクして見せた。
お互い表面状はほとんど変わらなくても、いつしか馴染んでしまったのは、否定出来ない事実だった。
一応、古くから通いで、手伝いの者はいるのだが。
配達にやってきたついでにガウリイは、その者達の気の回らない、家の細々とした雑用などを片付けてくれるようになり、老人の方も、わざとそれを片付けないままにしておくようになっていた。
連れ合いや子供達が逝ってしまってから、この広い家に、彼等以外の人の気配がするのは久し振りだったが、この新参者が決して不快ではなくなっているのが不思議だった。
それが何を意味するのか、近頃、ようやく判った気がしていた。
「相変わらず、末娘の尻にひかれておるようじゃな」
老人の言葉に、暖炉の前の床に陣取っていたガウリイが振り返ると、今までとはちょっと違う笑顔が浮かんでいた。
照れたような、困ったような、微妙なニュアンス。
「ひかれてるつもりはないんだけどなぁ。
やっぱり、そんな風に見えるのか?」
頭をかく彼に、老人は茶を一口飲んでから、再び言葉を紡ぐ。
「わざと、ひかれてやっておるんだろ?」
ガウリイの顔から、ふっと笑みが消えた。
「……じーさん…」
「あの娘は、性根は悪くないが、まだまだコドモじゃ。
それで釣り合いがとれるのだろうよ」
ガウリイは暖炉の方から、老人の方へ胡座をかきなおす。
「おまえもそれでよいと思ってるなら、好きにするがいいさ」
静かに目を閉じてから、いつもとは違う微かな笑みを見せるガウリイ。
「ああ」
「――おまえも多分、大事な人間を沢山亡くしてきたんじゃろう?」
「――じーさんもな」
初めて、老人の顔に、僅かに笑みが浮かんだ。
「あんまり相手が大事過ぎると、そうなるモノさな。
相手の幸せが、自分のそれになっちまう――」
「でも、それでもかまわない」
「そういうことじゃ」
ガウリイは暖炉の上に置かれている、小さな肖像画の額に目をやり。
「いまでもホレてるんだろ?」
「あたりまえじゃ」
「いい女だった」
「世界一のな」
「オレのリナもだぞ」
「おまえだけに、じゃろ」
「じーさんもな」
老人は、くすっと鼻で笑った。
「――この家はな、あれのために建てた。
あれがここにいて、息子達がいるのを見るのが――何よりも、幸せだった……」
皺の深く刻まれた目尻に浮かぶ光るモノを、ガウリイは切なげに目を細めて見つめていた。
今はただ、独り取り残された広い立派な屋敷が、老人の想いの行き場なのだろう。
そして、間違いなく自分も知っている。
愛した者達が、永久に失われてしまった喪失感を。
その大きさを、重さを。
この老人にとっては、おそらくは誰も埋めることの出来ない空白だったからこそ、心を閉ざすしかなかった。
そうしてしか、生きてこられなかったのだろう。
―――今までは。
「――そんなにいい連れ添いだったなら、自慢してやれよ」
驚いたように老人は、ガウリイに視線を戻した。
「じーさん以外、誰も知らないなんて、もったいないじゃないか」
少しとぼけたような口調。
「だから、おまえは吹聴しとるのか」
「そういうことだ」
ガウリイはまた嬉しそうに笑い。
「だから、若いモンは臆面のない…」
「いいじゃないか、自分の女房のことなんだから」
「雑貨屋の末娘が、それほどいい女とは思えんがな」
「いい女になる、のさ。オレがしてみせる」
「えらいホレ込みようじゃな」
「そりゃ、な。あれ以上の女はいないって」
またため息をついた老人の目からは、もう哀しみは消えていた。
どんどんどん………
「お?」
再びのドアを叩く音に、ガウリイが腰を浮かせ。
「――リナだ。
何であいつが来るんだ?」
「見んでも判るのか」
「そりゃ、ホレ込んでるからな」
玄関に出て行くガウリイの背中を、老人は苦笑で見送った。
「ガウリイ!」
「リナ、どうしたんだ?」
「どうした、じゃないわよ!
あんた、用を済ませたらさっさと帰ってきなさいって言ったの、忘れてるでしょ!?」
雨は少し小降りになってきたとはいえ、玄関先に立っているリナは、全く濡れていなかった。
おそらくは『翔封界』を使って、雨を避けるのと急いで来るのを兼ねたのだろう。
「―――だっけ?
だって、『邪魔だからどっか行ってろ』って言ったのおまえじゃないか」
「だぁかぁらぁっ!
その後で、そう言ったでしょうにっっ!!」
「もう帰ってもいいのか?」
リナの顔が引きつった。
「―――ガウリイ〜〜。
あんた、もしかしたら、今日が何の日か忘れて…る?」
「――今日?
何かあったっけ?」
ぱっこ―――――んっ!
広い屋敷に、やたらと軽い殴打音が響いた。
「あんたねぇぇっ、自分の『誕生日』忘れてどーすんのよっ!!」
しかし、変わらずきょとんとしているガウリイ。
「そうだっけか?」
ぱこ、ばこ、ぱっこ―――――んっ!
連続の殴打音を聞きながら、老人は静かに立ち上がると、玄関と反対の方に向かった。
「だからねぇ、お祝いの用意してるのに、あんたがいちゃ困るからって追い出したんでしょうにぃぃっ!」
すっかりテンションが上がってしまったリナを、ガウリイがぎゅっと抱きしめる。
途端、真っ赤になるリナ。
「ちょ、ちょっと、ガウリイっっ!
こんなトコで何すんのよぉぉっ!!」
「――やっぱり、最高だよ、おまえは」
照れでじたばたともがくリナを、すっぽりと腕の中に納めてしまったガウリイは、本当に幸せそうな表情をしていた。
「おい」
さっき入って行った奥の部屋から、老人が顔だけ出して呼んだ。
「ん? 何だー?
リナ、ちょっと待っててくれ。
すぐすませてくるから」
名残惜しそうに離し、軽いフットワークで部屋に消えていく夫を見送りながら、リナは玄関ドアを後ろ手に閉め、少々不満そうに息を漏らした。
そして、家の中を見渡す。
考えてみれば、この家に入ったのは初めてだった。
出入りしていた父が言っていた通り、確かに立派な屋敷である。
足腰の弱った老人の一人暮らしでは、手入れも行き届かないと思うのだが、人でも雇っているのか、全く荒れた感じはない。
逆に、なまじ広くて綺麗な分、沈黙が重く伸し掛かってくるようで。
立派な調度には目を引かれたが、こんな所で暮らすのは、ごめんだという気がした。
「よ、待たせたな」
しかし、それもガウリイが戻って来ると、不思議と中和されたような感覚があり。
その意味がリナにはよく判らなかったが、ここによく来ているせいだろうと解釈する。
「じゃあ、じーさん。またな」
「ああ」
「すっかり馴染んじゃったみたいね」
後から出てドアを閉めたガウリイに、リナが言った。
「そっか?」
「父ちゃんが言ってたわよ。
あの爺さんは食えない、って」
「あれでも、いいじーさんなんだぜ」
「そぉお?
あたしにはそうは思えないけど――」
「ま、今にわかるさ」
ガウリイは、恋女房の頭を撫でた。
その後、新婚夫婦の新居にリナの両親と姉のルナも集まって、楽しい宴が催された。
もっとも、主役に自覚が足りないせいか、誕生パーティというよりは、単なるどんちゃん騒ぎという様相を呈していたが。
やがて、日付が変わる頃、来訪者達は帰って行き―――。
「おーい、リナ。
後片付けは明日にして、もう休めって」
「でも〜、いっぱいあるんだもん」
酒のせいか少々おぼつかない足取りで、居間から台所に向かおうとするリナを、ガウリイが抱き上げた。
「ちょっと! ガウリイっ!?」
ガウリイはそのままリナを片手で支えると、さっきもらったばかりのいくつかのプレゼントを、散らかったままのテーブルから拾い上げ、持たせた。
さすがにそれを落とすわけにはいかず、リナはおとなしくするしかなくて。
寝室に入って、ようやくベッドに降ろされると、唐突にガウリイが言った。
「オレ、リナから欲しいモノがあるんだけどな」
「へ?
さっき、これあげたじゃない!」
リナは自分の抱えたままの包みを示す。
その中には、彼女のお手製の上着が入っている。
それが不満だとでも言うのだろうか?
「わかってる。でも、どうしても、もう一つ」
「………いつから、そんな欲張りになったのよ」
「おまえのことだけな」
ガウリイはベッドの脇に膝を付いて、リナと向かい合わせになった。
いつになく真摯な視線に真正面から見つめられて、リナの頬が染まる。
「………何が欲しいわけ?」
にっこり笑ったガウリイは、ポケットから何かを取り出した。
その反対の手でリナの手を引き、握ったままの拳を乗せる。
大きな手が除けられた時、そこには綺麗なブローチがあった。
目の利くリナには、その見事な細工と宝石の価値が、すぐに判断出来て――。
「ちょ、ちょっと、どうしたのよ、これ!?」
間違いなく、そう簡単には手に入らない程の逸品だ。
「じーさんからの、バースディ・プレゼント。
連れ合いの形見なんだってさ。
おまえにやるよ」
「はあ!?
それじゃ、あんたがもらったんじゃない!
あたしにくれてどうするのよっ!」
リナは慌てて、押し返そうとする。
自分の手で、小さな手ごとそれを包み込むようにして、握らせるガウリイ。
「いいんだよ。
じーさんが言ったんだ。
『おまえがこの世で一番もらって嬉しいのは、女房の幸せな笑顔なんじゃろ?
これをやるから、自分の力で調達するんじゃな』ってさ」
「……………」
視線を手に落として沈黙してしまったリナを、ガウリイが困ったように覗き込む。
「リナ?
これじゃダメだったか…?」
「………ばか…」
リナはそのまま、ガウリイに抱き付いた。
「ほんとに、ばかなんだから…!」
ひとしきり抱き返すと、また顔を覗き込むガウリイ。
「くれるのか?」
リナは、さらに頬を染めると、今度は真っ直ぐ視線を合わせて―――。
「誕生日おめでとう、ガウリイ」
その笑顔が、絶品だったのは言うまでもなく。
もしかしたら。
希代の自称愛妻家も、かつてこのようにしたのかもしれない。
――何はともあれ。
先達<せんだつ>の粋なはからいで、その日はガウリイにとって、今までで最高の誕生日になったのは間違いない――。