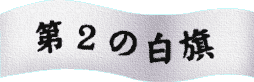
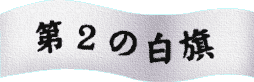
「ルナおばしゃん、おかえりなしゃーい♪」
帰宅したルナ=インバースを玄関先で満面の笑みで出迎えたのは、姪のレイナだった。
「ただいまー、よく来たわね、レイナ」
軽い動作で抱き上げてやると、小さな子供特有なすべすべした感触の心地いい頬ずりが来る。
「きょう、おしごとはやかったんだね」
「早番ってわかる?」
「なーに、それ?」
いつものごとく、姪っ子の聞きたがりに付き合いながら、家の中へ。
とは言え、この二人、最も肝心な話を何もしていない。
つまり――早番というモノすら知らないレイナが、どうしていつもより早いルナの帰宅がわかったのか、とか。
姪以外の妹一家はどうしているのか、とか。
まあ――後者に関しては、廊下の向こうから聞こえてくる男の子達の喧騒からも十分察せられるとしても。
人間の範囲を遙かに凌駕したようなこの二人にとっては、ヒトの気配を感じるコトなど不思議でも何でもないらしい。
「おばちゃん、お帰りー」
「お帰りなさい、ルナおばさん」
「お疲れー、おばさ〜ん」
自分達の家と同じ調子で、慣れ親しんだ廊下をころころと遊び回っている甥っ子達から、各々の性格まんまの挨拶が飛んでくる。
「ただいま」
にっこり笑いながら、一番近くにいた双子の次男坊・バクシイの頭を軽くこづく。
「ってぇ! 何すんだよ、おばさんっっ!」
「あんただけ、違う意味で言ってたでしょ。
確信犯でモノを言うのはよしなさいって、教えなかったかしら?」
ぶーたれた表情をしながらも反論してこないのは、核心を突かれたからだろう。
もっとも、『赤の竜神の騎士』の名を冠する伯母を畏怖するどころか、全く平気でこんな口利きが出来るのは、相当の度胸があるとも言うけれど――。
性格的に妹のリナに一番似ているのは、この次男坊かもしれない、と近頃ますます思う。
「かくしんはんってなーに?」
そのニュアンスを、この至って素直なレイナにどう伝えていいものやら。
苦笑しながらルナは居間のドアを開いた。
「よぉ、ルナ。おかえりっ」
「姉ちゃん、お帰り〜」
入って左側の長椅子に妹夫婦――リナとガウリイが、反対の台所側には両親が座っていて、それぞれから声がかかった。
店はどうしたの?と訊こうとして、思いとどまる。
この孫が可愛くて仕方ないの両親のコト、おおかたいきなり臨時休業にでもしてしまったのだろう。
「お、レイナ。
トイレでも行ったのかと思ったら、おばちゃんを迎えに行ってたのか?」
「うんっ、おじーしゃん。
ルナおばしゃんつよいから、よくわかるんだもん」
もちろんこれが物理的な意味ではないのは、ここにいる全員、もう周知の事実で。
つまり――存在感というか、発する気の強さのコトを言っているらしい。
居間に、香ばしいいい香りが漂ってきた。
「――パイが焼けたようね。
さ、お茶にしましょ」
ルナ、リナ手伝って。ガウリイは男の子達を呼んで来て」
母の指示で、ルナは抱いていたレイナを父に手渡す。
「はい、お父さん。お宝を渡すわね」
「おう」
「おたからって?」
「お前のことだよ」
「えー? じゃあ、おにーしゃんたちはちがうの?」
早速始まった聞きたがりに困る父を背に、ルナは台所に向かった。
どの孫も分けへだてなく可愛がっている父だが、最後に生まれた妹のリナそっくりのレイナは特に溺愛している。
とは言え、元は歴戦の勇士と言えど、この聞きたがり攻撃には楽勝と行かないようだ。
ガウリイが一人で戻ってきた。
「おう、どうした天然。
また用事でも忘れたか?」
義父のツッコミに、婿は苦笑するしかない。
「坊主達は手を洗いに行ったんだよ」
「おとーしゃん、こっちおいでよー」
それでも愛娘の要求に応えて、隣に腰を下ろす。
しかし、当の舅には可愛い孫娘を渡す気など毛頭なさそうだ。
彼にしてみれば、ガウリイは常日頃独占しているのだから、だそうだが――それは無茶とも言う。
それでもしかたないと思っているのか、世間では『らぶらぶ父娘』と呼ばれる程に懐かれていることに自信でもあるのか。
ガウリイは伸ばされたレイナの小さな手を、きゅっきゅっと握手するように握ってやっただけだった。
「ねー、おじーしゃん。
どーしておとーしゃんのこと、『てんねん』ってよぶの?
おとーしゃんきらい?」
ぴききききぃっ。
その瞬間、部屋の空気が一気に凍り付いた。
「ど、どうしてだ?」
何とか引きつった笑顔を取り繕った祖父に、孫娘は容赦ない質問を浴びせる。
「だってー、そうよぶときだけ、ちょっとおじーしゃんね、うーーーーんと……くろいの」
幼いながらに何とか表現を探してのコトなのだろうが、意味する処は大人2人にはよーくわかったらしい。
「レイナね、おじーしゃんはくろくないほうがすきなの。
だからね、そうよばないでほしいの」
必殺技『小首傾げ』を至近距離で食らった舅を、ガウリイが横からじっと見ている。
「だめ?」
冷や汗を一筋流した後、祖父はぼそっと言った。
「――わかった」
途端にレイナの顔が輝き、しがみついてくる。
「おじーしゃん、だいすき!」
柔らかな金色の巻き毛を撫でながら、義父は複雑な表情で、横にいるその遺伝子の元になった男を見つめ返していた。
居間に入ってきた兄達に、大喜びで報告しに駆け寄っていくレイナの背を見ながら、今度はガウリイが呟いた。
「一本取られたな」
「おまえに負けたわけじゃねぇからいいんだ、天然」
「――そう呼ばないって言ったばかりだろ?」
「バカ野郎。
それはレイナの前でだけだ」
ガウリイは苦笑ともあきれ顔ともつかない表情をした後、軽くため息をついた。
インバース夫人が可愛い孫達のために作った様々なパイが、居間のテーブルにずらりと並べられる。
「さあ、何がいい?」
『えー!?』
リナの問いに、抗議のハモリ。
「あんた等ねぇ〜」
「いいじゃねぇか、全部切ってやれば」
「そうよ、まだあるんだから」
祖父母は爺婆バカっぷり、丸出し。
――確かに1ホールくらい平気でたいらげるような子達だけどさ。
リナはため息をつきながら、切り分けに入る。
「オレも頼むなー、リナ」
のんきな亭主には、しっかり一撃を見舞いながら。
「――なあ、レイナ。
その『黒い』って、なんなんだ?」
長男坊のガルデイの問いに、おかわりのパイを自分の皿に乗せていたリナは思わず手を止める。
バクシイの横に座っていたレイナは、ちょっと悩んだ顔をしてから、次兄を見上げた。
「うーんとね。さっきバークおにーしゃんが、ルナおばしゃんをよんだときみたいなかんじなの」
一斉に皆の視線が、バクシイに集まる。
「おいおいっ!?
どーいう話だよ、レイナっ!」
「よくわかんないんだけど……、ルナおばしゃんはわかる?」
今度は、トレイにお茶のおかわりを乗せて入ってきたルナに視線移動。
でも、『赤の竜神の騎士』はいたって冷静な笑顔で答える。
「侮蔑のニュアンスを感じるってことでしょ?」
「侮蔑って何だ?」
そう訊いたのは、ガウリイ。
リナは頭を抱えている。
――子供と一緒か、あんたはっ。
謎の三男坊・ラグリイが、ミルク入りのマグカップを持ったまま、ぼそっと口を開いた。
「母さんがケンカした時、父さんに向かって、『バカ』って言うのと同じだろ?」
しーん。
大人全員硬直。
兄達二人はシンキングタイム。
末姫様だけが、すぐににっこり笑った。
「そっかー、だいすきだけど、ちょっとだけきらいっておもっちゃったときに、そうなるんだね?」
決してそれが真理ではないコトを、大人達はよく知っている。
けれど、それは大人達の機微。
誰一人として子供――ましてこの負の感情と極端に縁のない末姫様を、十分納得させるに足る説明など出来るはずがなかった。
「けどさぁ、ルナおばさんがおれたちの『おばさん』なのって、どう呼んでも変わりないじゃん?
だいたい、ヨソの人たちだって『おばさん』って呼ぶじゃないか。
そんなのイチイチ気にしてらんないって」
バクシイのバツの悪そうな意見に、レイナがまた兄の顔を見上げて、小首を傾げる。
「ちがうよ、バークおにーしゃん。
ほかにもたくさんすきな『おばしゃん』や『おじーしゃん』はいるけど、レイナたちのホントの『おばしゃん』と『おじーしゃん』は、たったひとりしかいないもの」
今度は、ガウリイの方を向いて。
「おとーしゃんにはもう、『おじーしゃん』たちはいないんだよね?」
苦笑気味にうなずく父に、レイナも深くうなずき返す。
「『おばしゃん』も『おばーしゃん』も『おじーしゃん』も、だから、レイナたちにはとくべつなの。
とってもたいせつなの。ね?」
いつも通り、要領の悪い説明ながら。
小首を傾げたまま、極上の微笑みを浮かべた末姫様に、部屋の中はすでに常春と化していた。
「泊まっていけばいいのに。どうしても帰っちゃうの?」
インバース夫人は名残惜しそうに、孫娘を玄関先でぎゅっと抱っこしている。
しょっちゅう泊まらせているというのに、どうにも離しがたいようだ。
「うーん、レイナね、ひとりでねるれんしゅう、そろそろしなきゃダメだって、おかーしゃんがね――」
「まあ、まだいいでしょうに。そんなのは何も急がなくっても――」
同じ名残を惜しむのでも、ガルデイとバクシイは、垣根越しに隣家の犬を撫でまくっている。
犬の方も、尻尾をちぎらんばかりの勢いで飛びついて喜んでいる。
舅と婿は、玄関ポーチの脇でまた低い声で話をしていた。
「――やーれやれ、とんでもない娘を作ったもんだな」
「可愛がってるくせに」
「可愛いから、余計に始末が悪いんじゃねぇか。
――ったく、俺にまた白旗上げさせやがって」
「――また、って、他に誰かいるのか?」
ガウリイの素朴な問いに、義父の視線が一瞬、孫娘を抱いた連れ合いの所に行った。
「――ああ、なるほどな」
「そういうトコだけ気付くんじゃねぇよ、この天然がっ」
殴りたいのを堪えたのは、注目されたくなかったからだろうか?
そっぽを向いた義父の頬は、いつもより赤みだった。
そこからちょっと離れた玄関の中では、姉妹同士が話していた。
横でラグリイがしゃがみ込んで、靴の汚れを拭いてる。
「――気を付けてやることね」
「十分、気を付けてるわよ。目を離したら、何するかわかんないんだから」
「そういう意味じゃないわ」
ルナが意味深に微笑んで、ラグリイの頭を撫でる。
「この子も多少はそうだけど、あの子は特に御せない何かを持ってる」
微妙な表情をしている末息子を、リナは不思議そうに覗き込む。
「ラーグ、あんた抱っことか撫でられるのって嫌がってなかった?」
拒絶という程ではないが、人懐っこい子供達の中で唯一、ラグリイは人に対して難しい子だったりする。
ガウリイあたりは『人見知りじゃないのか?』などと、お気楽なコトを言っているが。
まあ、こんな風に身内にはそれなりに接しているコトから考えると、スキンシップが嫌いとか言う訳でもないらしい。
「ルナおばさんならいいよ。
他の人たちとちがって安定してるから、さわられててもしんどくないもん」
「はあ?」
素っ頓狂な声を出した母を置いてきぼりにして、相変わらず不思議な三男坊は兄達の所に行ってしまう。
「ちょ、ちょっと!」
「ラーグも、一筋縄ではいかなさそうね」
「ねぇ、じーちゃん」
「おう、ガル、どうした?」
末弟と入れ替わりに、長男のガルデイが祖父の元にやって来た。
「今度さ、剣のけいこにつきあってくんない?」
「いいぞ。親父じゃ役に立たんのか?」
「あのなぁ」
ガウリイが頭をかいている。
ガルデイが笑顔になるとそれこそ父親そっくりなのだが、祖父の欲目か、その点は気にならないらしい。
「父ちゃんばっかとやってたら、戦い方かたよっちゃうだろ?
おれさ、剣士の父ちゃんに負けないようになりたいから、いろいろおぼえたいんだ」
「よーし、わかったわかった。
早くこいつをブッ倒してやれ」
意気揚々と言う祖父に、ガルデイはあっけらかんと言い放った。
「ちがうって、じーちゃん。
父ちゃんを倒したいわけじゃなくて、あこがれてるから追いつきたいんだって。
それからのことは、またかんがえる」
当のガウリイは、気の利いたフォローなどもちろんできるはずもなく、ぽりぽりと頬をかいていた。
そのやりとりを聞いていたルナはくすくすと笑っている。
「ほんとうにどの子もいろんな素養たっぷりで、育て方次第ではさぞかし面白いコトになるかも」
「姉ちゃん――自分の甥姪で遊ばないでくれない?」
「だって、あんたとガウリイの子供達だもの」
リナは引きつった顔で、ルナを見る。
「それ――子供達には言わないでよね」
「あら? 本当の事じゃない?
何か『変な事』言ったかしら?」
何もかも知っているクセにひょうひょうとしている姉の態度に、リナは唸るしかない。
「どうせすぐに大きくなって、親なんか相手にしてくれなくなるわよ。
せいぜい楽しむ事ね」
インバース家からガブリエフ家まで、子供達の足でもそうかかるわけではなく、いつもの慣れた道中だった。
はしゃぎながら先を行く子供達の後に、リナとガウリイがのんびりと散歩のような足取りで付いていく。
両親のらぶらぶぶりをよく知っている子等は、こんな時は決してジャマしたりしない。
しかしそれを言うと、照れ屋のリナが近所迷惑な呪文を炸裂させるので、あえて約束事にはなっていないのだけど。
満月の光の中、いつものごとく歩いていたガウリイが、ふと小さな声で呟いた。
「オレのはとっくに揚がってるよな」
「へ?」
「な?」
唐突な言葉に付いて来れずに見上げてきたリナに、ガウリイは昔のままにっこりと笑う。
少し頬を赤らめながら、リナは問う。
「何がよ?」
「白旗」
「はあ???」
ガウリイは軽く笑いながら、リナの肩を頭ごと抱き寄せる。
そう、リナに出会って保護者を買って出たその時から、とっくにそんなモノは揚がっていて。
今はまた、目の前にいるリナとの子供達にも揚げているのだろう。
でも、それは何一つ屈辱などではなくて。
それどころか、自分の何に替えても守りたいと思える大切なモノを持てたコトが誇らしく、そのまま幸せなのだと――ガウリイには素直に思えていた。